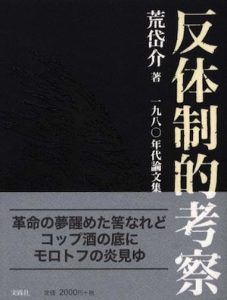桜の季節、やっぱり内尾のことを書いておこう。
22年前、大学院生だった僕に心理学科のH先輩から電話があった。彼の職場である内尾センターで美術の講師をしないかというのだ。僕はいつもの癖で軽くかるーく引き受けた。だが大学院の指導教官のE先生は「そんな責任の重いことは僕は賛成できない」と言った。

内尾センターは岡山県が運営する精神障害者の施設である。E先生は僕のような半端な人間がそんな人の心に関わるような仕事をすることを心配されたに違いない。今思えばまったくその通りだ。だが結局僕はホイホイと乗り込み、内尾センターが閉所になるこの三月まで美術と木工の講師を勤め通してしまった。
この22年を思い出すとちょっとくらくらする。あまりにいろんなことがあった。いろんな人と出会った。
「うるせーわい!」と怒鳴って喧嘩をしたことも何度かあった。喧嘩の相手はいつも利用者(患者のことをこういう)だった。「相手は病気なんだから」とうまく受け流すことがどうしてもできなかった。最後はいつも利用者が謝ってくれた。E先生の心配は当たっていたし、それ以上に利用者は僕より大人だったということだろう。
内尾センターが閉所になった理由は県の財政の問題だったと思う。利用者やその家族会は必死で存続運動を闘ったが最初から結論が出ているストーリーの中では無力だった。日本の役人世界は外国に対してははなはだ交渉下手だが、自国の国民に対しては実にうまい。「貴重な意見を真摯に受け止め、きちんと対応して、やるべきことを粛々とおこなって」いつのまにか内尾は終わってしまった。
書類上は三月一杯だが残務整理の関係で実際には二月で利用者は存在の場所を失った。僕も二月二十八日の木工を最後に内尾を終えた。十日ほど経って用事ができて僕は利用者のいなくなった内尾に行った。木工担当のIさんが木工室の最後の片づけをしていた。Iさんは自分の休みの日まで内尾に出てきてあれこれ仕事をしてくれた。小柄なのにえらい馬力の御仁で僕は随分助けられた。その馬力の最後をやけくそのように発散して木工室は大型の機械を残して見事に何もなくなっていた。僕の混沌とだらしなさをそのまま形にしたような木工室のすべてが消えていた。だが不思議なことに何もなくなった空間は逆に空気が濃密になるようだ。今を失って降り積もった過ぎし時間があらわになる。僕は言葉を失い、しばらく立ちつくしていた。職員達は美術と木工の時間のことを「矢野ワールド」と呼んでいた。僕にはわからないがたぶん妙な臭いがしていたんだろう。それは僕が一人で作っていたのではなく、その時間に参加していた利用者と僕との関係が作っていた「臭い」だったと思う。
いつもぎこちなく心打つピアノを聞かせてくれたT君、どでかい絵を描くN君、なぜか同じ言葉を三回ずつ繰り返し、モデルそっくりの人物画が描けてしまうHさん、自衛隊の潜水艦乗り上がりで大型のいたずらっ子みたいだったMさん、二年がかりで瀬戸大橋の模型を作ったM君、突然尾崎豊の歌真似パフォーマンスをどこでも始めるK君、ジャズギターの名手だったY君……その他この部屋で僕とともに長い時間を過ごしてくれた人々。
ありゃりゃ? なんだかセンチメンタルな気分になってきた。違う違う! じゃなくって僕が書いておきたかったのは木工室がびっくりするほどきれいになってみて初めてわかったことだ。それはあふれだした「もの」が醸し出すある種の優しさ、許してくれる雰囲気のこと。たぶんそれは「もの」の背景にある人という存在の可愛らしさみたいなものが空間をなごませているんじゃないだろうか。それは厳しい清潔な生き方のできる人から見ると我慢のならないだらしなさと見えるものかもしれないが、少なくともこの木工室に集まってきた人々には必要な混沌だったと思う。でも確かにいざ作業をしようとするとこの混沌は困った。時間の半分ぐらい捜し物をしていた。かんな、のみ、接着剤、図面、いつも何かを探していた。それはまさに僕という人間の混乱そのものであり、内尾ボーイズ(実は僕は彼らのことを密かにそう呼び慣わしていた)の人生そのものであったかもしれない。捜し物に疲れると僕はよく木工室の裏にある三段の階段に腰掛けて煙草を吸った。僕がそこにいるといつのまにか誰かが隣に腰掛け、とりとめのない話をした。敷地内にはたくさんの桜の木があった。この季節、桜を眺めながら内尾ボーイズと交わした妙にシュールな時間は、もしかしたら僕の人生の中でもっとも美しい絵であったかもしれない。
巣を追われた内尾ボーイズはこの後もう一度居心地のいい場所を見つけ出せるだろうか。彼らには悪いが僕には工房という居場所がある。ここは実のところあの失われた木工室以上に散らかっている。僕のいる所どこでもこうなる。残りの人生をやっぱり何か探し続けるというのは気が重い。どうにかならんかなあ……